税理士事務所のホームページ、制作会社 vs 自作のリアルな比較

独立開業の準備を進めている先生、あるいは、すでにご活躍中の先生も、「うちの事務所も、そろそろホームページくらいは持っておくべきかな…」と考えたことが一度はあるかもしれませんね。
紹介だけで十分お客様はいるし、そもそも忙しくてそんなことに時間は割けない。そんな声も聞こえてきそうです。
でも、新しいお客様が顧問税理士を探すとき、まず何をすると思いますか?
そう、インターネットで検索するんです。
その時に、事務所の顔となるホームページがあるかないかで、信頼性や印象は大きく変わってきます。
問題は、その「作り方」ですよね。プロの制作会社にしっかりしたものを作ってもらうか、それともコストを抑えて自分で作ってみるか。これは、多くの先生が悩むポイントだと思います。
今回は、この二つの選択肢について、どちらが良い・悪いという話ではなく、それぞれの「リアル」な部分を、一緒に見ていきたいと思います。
「餅は餅屋」か「自分で挑戦」か。運命の分かれ道

ホームページ作りを考えたとき、目の前には大きく二つの道が広がっています。
一つは、専門家であるホームページ制作会社に依頼する道。もう一つは、自分でツールを使って作成する道です。
どちらの道を選ぶかで、見える景色はかなり変わってきます。
制作会社に依頼する道
こちらは、いわば「フルオーダーのスーツを仕立てる」ようなもの。
担当者と打ち合わせを重ね、事務所の強みや理念、ターゲット顧客などを伝えます。デザインや構成、文章作成(ライティング)まで、専門家チームが先生の想いを形にしてくれます。
もちろん、その分費用はかかりますが、完成度の高い、信頼感のあるホームページが手に入る可能性が高いです。
自分で作成する道
こちらは、「既製品の服を自分でコーディネートする」イメージに近いかもしれません。
最近は、専門知識がなくても直感的に操作できるホームページ作成ツールがたくさんあります。テンプレートを選んで、写真や文章を入れ替えていくだけで、それなりの形にはなります。
最大の魅力はコストを抑えられること。ただ、デザインの自由度や機能には限りがあり、どこまでこだわるかによっては、思った以上に時間がかかることもあります。
どちらの道が正解、というわけではありません。
大切なのは、先生の事務所の今の状況(予算、時間、目的)に、どちらの道が合っているかを見極めることです。まずは両方の特徴をしっかり把握することから始めましょう。
【徹底解剖】制作会社と自作、5つのリアルな比較軸

では、具体的にどんな点が違うのでしょうか。
経営者である先生方が特に気になるであろう「費用」「時間」「クオリティ」「運用」「集客」という5つの軸で、リアルな違いを比較してみます。
| 比較軸 | 制作会社に依頼 | 自分で作成 |
| 初期費用 | 数十万円〜数百万円が相場。機能やページ数による。 | 0円〜数万円程度(有料ツールの契約料など)。 |
| ランニングコスト | サーバー・ドメイン代、保守管理費で月額数千円〜数万円。 | サーバー・ドメイン代、ツール利用料で月額0円〜数千円。 |
| 制作時間(手間) | 打ち合わせや原稿確認が中心。実作業はお任せできる。 | デザイン選定から文章作成、画像準備まで全て自分で行う。 |
| クオリティ | プロが作るため、デザイン性・信頼性が高い。独自機能も実装可能。 | テンプレートに依存。オリジナリティを出すのは難しい場合も。 |
| 更新・運用 | 更新作業も依頼する場合、費用と時間がかかることがある。 | 自分でいつでも好きな時に更新できる。 |
| 集客(SEO) | 専門家によるSEO対策が期待できる。 | 自分で勉強して対策する必要がある。 |
比較軸1:費用(初期コストとランニングコスト)
やはり一番気になるのはお金の話ですよね。
制作会社に依頼すると、初期費用としてまとまった金額が必要になります。一方、自作なら初期費用はほぼゼロに抑えることも可能です。ただし、自作でも有料のテンプレートを使ったり、高機能なプランを契約したりすると、数万円程度の初期費用がかかることもあります。
比較軸2:時間と手間
「タイムイズマネー」は、先生方が一番よくご存知のはず。
制作会社に依頼すれば、面倒な作業はほとんどお任せできます。先生がやるべきことは、打ち合わせで要望を伝え、出来上がってきたものを確認・修正するくらいです。一方、自作の場合は、ツールの選定から使い方を覚え、コンテンツを考え、写真を準備し…と、想像以上に時間が溶けていく可能性があります。
比較軸3:クオリティ(デザインと機能)
ホームページは事務所の「顔」。その見た目は非常に重要です。
制作会社は、事務所のブランドイメージに合わせたオリジナルのデザインを提案してくれます。士業としての信頼性や権威性を表現するデザインも得意です。自作の場合は、どうしてもテンプレート感が出てしまいがち。ぱっと見で「ああ、このツールで作ったんだな」と分かってしまうこともあります。
比較軸4:公開後の更新・運用
ホームページは作って終わりではありません。
法改正があったり、新しいサービスを始めたりした時に、情報を更新していく必要があります。自作なら、管理画面から自分で手軽に更新できます。制作会社に依頼した場合、簡単な更新は自分でもできるようにシステム(CMS)を組んでくれることが多いですが、大幅な修正は都度依頼となり、費用や時間がかかるケースもあります。
制作会社に依頼する場合は、「ブログやお知らせなど、どこまで自分で更新できるのか」を契約前に必ず確認しておきましょう。更新のたびに費用がかかる契約だと、ランニングコストが想定以上にかさんでしまう可能性があります。
「自分で作る」と決めた先生へ。代表的なツールの特徴

もし「まずはコストを抑えて自分でやってみよう」と決めたなら、次に考えるのは「どのツールを使うか」です。
ここでもいくつかの選択肢があります。
WordPress(ワードプレス)
世界で最も使われているホームページ作成システムです。ブログ感覚で更新でき、デザインテンプレートや拡張機能(プラグイン)が豊富なので、やろうと思えば何でもできます。その分、サーバーの契約やインストールの設定、セキュリティ対策など、専門的な知識が少し必要になります。自由度の高さと引き換えに、管理責任もすべて自分にある、というイメージです。
ホームページ作成サービス
専門知識がなくても、ブラウザ上でホームページが作れるサービスです。有名なものには「Wix(ウィックス)」「Jimdo(ジンドゥー)」「ペライチ」などがあります。サーバーの準備も不要で、アカウントを登録すればすぐに始められる手軽さが魅力です。
ただし、無料プランは広告が表示されたり、独自ドメインが使えなかったりする制約があることがほとんど。ビジネスで使うなら、月額1,000円〜3,000円程度の有料プランが基本になります。
- ・信頼感のあるデザインか?:奇抜さよりも、誠実さや清潔感が伝わるテンプレートを選びましょう。
- ・独自ドメインは使えるか?:「〇〇-tax.com」のような独自のURLは信頼性の証です。有料プランの機能を確認しましょう。
- ・SSL対応は標準か?:通信を暗号化するSSL(URLがhttps://で始まる)は、今や必須です。顧客の情報を守るためにも必ず確認してください。
- ・ブログやお知らせ機能はあるか?:情報発信は専門性を示す上で重要です。簡単に更新できる機能があるか見ておきましょう。
あなたの状況別・実践的なアプローチ
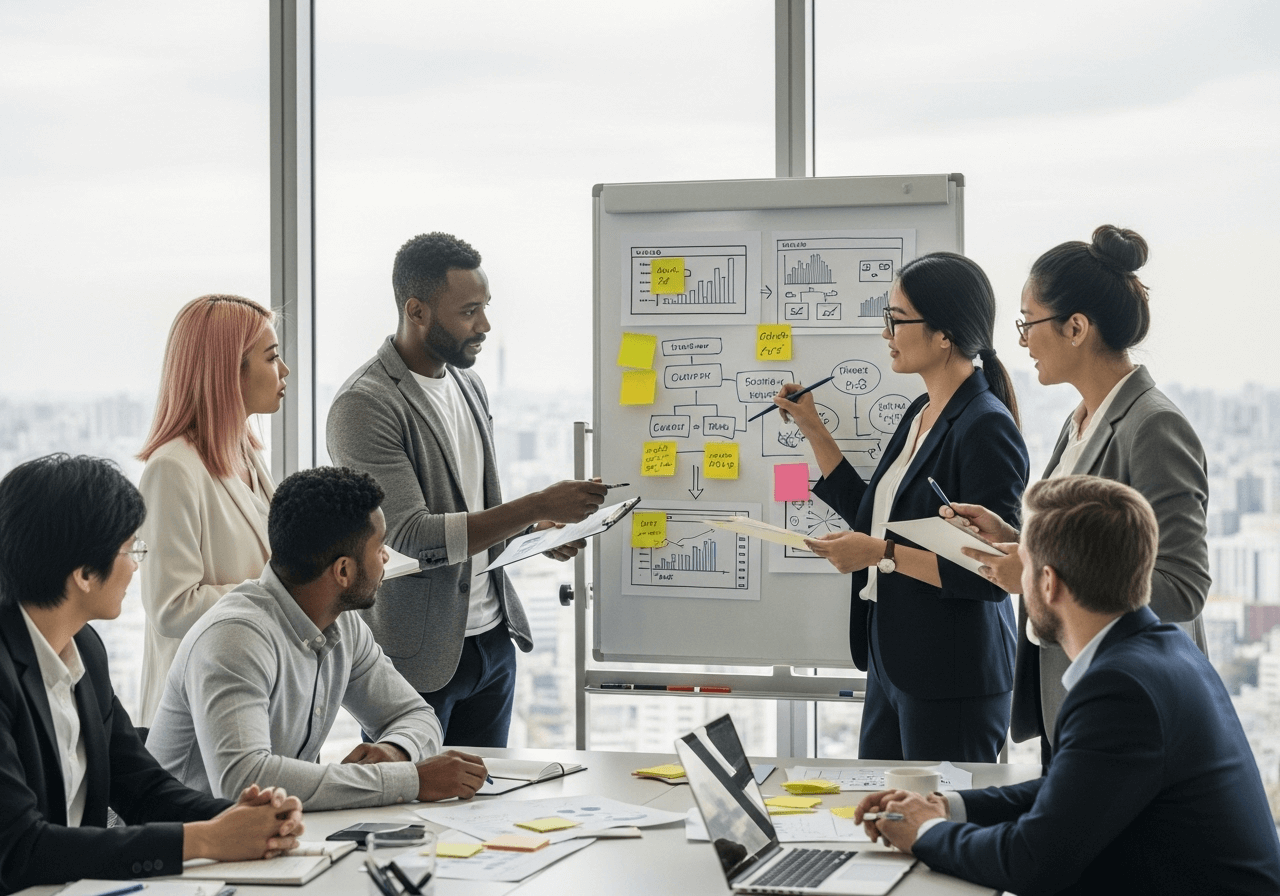
ここまで色々な情報を見てきましたが、「で、結局うちはどうすればいいの?」というのが本音ですよね。
そこで、事務所の状況別に、どんなアプローチが考えられるかを提案します。
開業したてで、まずは名刺代わりが欲しい先生へ
この段階では、大きなコストをかけるよりも、まずは「存在を証明する」ことが大切です。
おすすめのアプローチ:【自作(ホームページ作成サービス)】
まずは月額数千円程度の有料プランで、独自ドメインを取得し、シンプルなホームページを作ってみるのが良いかもしれません。事務所概要、代表者プロフィール、サービス内容、お問い合わせフォーム。この4つがあれば、立派な名刺代わりになります。
特定分野に特化して、ネット集客を強化したい先生へ
例えば「相続専門」や「医療法人特化」など、強みを打ち出してWebからの問い合わせを増やしたい場合です。
おすすめのアプローチ:【制作会社に依頼】
この場合は、デザイン性だけでなく、SEO(検索エンジン最適化)やWebマーケティングの知識が不可欠です。専門分野のキーワードで上位表示を狙ったり、ターゲットに響くコンテンツを企画したりするのは、プロの領域。投資対効果を考えて、実績のある制作会社に相談するのが近道です。
複数のスタッフで運用していきたい事務所様へ
所長だけでなく、他のスタッフもブログを更新したり、情報を発信したりしていきたい場合です。
おすすめのアプローチ:【制作会社に依頼 or 自作(WordPress)】
複数の人が関わる場合、運用のルールやマニュアル作りが重要になります。制作会社に依頼すれば、複数人での運用を前提としたシステム(権限設定など)を構築してくれます。もしITに詳しいスタッフがいるなら、WordPressで自作するのも一つの手ですが、セキュリティ管理の責任者を明確にしておく必要があります。
どちらを選んでも失敗しないための「共通の心構え」

制作会社に頼むか、自分で作るか。どちらの道を選んだとしても、これだけは押さえておきたい、という共通のポイントがあります。
「誰に」「何を」伝えたいのかが一番大事
ホームページは、単なるデジタルなパンフレットではありません。
「どんな悩みを持つお客様に」「自社のどんな強みで応えられるのか」というメッセージを伝えるためのツールです。これがあやふやなまま作っても、誰の心にも響きません。
制作会社に依頼するなら、この部分をしっかり伝える必要がありますし、自作するなら、まずこの点をじっくり考える時間を取りましょう。
作って終わり、では意味がない
これは本当に重要です。ホームページは生き物のようなもので、公開してからが本当のスタート。
お客様の声を追加したり、法改正に関するコラムを書いたり、セミナーの告知をしたり…。
常に新しい情報を発信し続けることで、検索エンジンからの評価も高まり、訪問者からの信頼も得られます。更新しやすい仕組みを確保しておくことが、成功の鍵です。
何を書けばいいか分からない…という先生は、普段お客様からよく受ける質問を思い出してみてください。「これって経費になりますか?」「確定申告で注意することは?」など、お客様が知りたい情報こそが、最高のコンテンツになります。
まとめ
税理士事務所のホームページ作りについて、「制作会社への依頼」と「自作」という二つの選択肢を、様々な角度から比較してきました。
- ・制作会社への依頼は、クオリティと信頼性を重視し、本業に集中したい先生向け。初期投資は必要ですが、プロの力で集客につながる強力なツールが手に入ります。
- ・自作は、コストを抑えたい、まずは名刺代わりから始めたい先生向け。時間と手間はかかりますが、手軽に始められ、自分でコントロールできる魅力があります。
- どちらを選ぶにしても、「誰に、何を伝えたいか」という目的を明確にすることが最も重要です。
- ホームページは作って終わりではなく、育てていくもの。更新・運用まで見据えて計画を立てましょう。
どちらの選択にも一長一短があり、正解はありません。今回の記事が、先生の事務所にとって最適な一歩を踏み出すための、良い判断材料になれば嬉しいです。
ホームページ作成ツールをお探しの方へ
ここまで税理士事務所のホームページ作りについて詳しく解説してきました。記事を読んで「実際に取り組んでみたいけど、やっぱり自分で作るのは大変そう…でも制作会社は高額で…」と思われた方に、少しだけ私達のサービスをご紹介させてください。
気軽にホームページが作成できる「PAGEKit(ページキット)」
「まずはホームページを立ち上げてみたい」「できるだけシンプルで分かりやすい料金体系がいい」と考えているなら、私たちが提供しているPAGEKitもご検討いただけると嬉しいです。
PAGEKitは、初心者の方でも安心してホームページが作れるよう機能をシンプルに、また、操作方法のお問い合わせにもすぐに答えられるようサポートをとても重視しています。
一人で悩みながら作るよりも、気軽に相談しながら作ってみませんか?
もちろん、この記事で紹介した他のサービスも、それぞれに優れた特徴があります。ぜひあなたの目的や予算に最も適した選択肢を見つけてくださいね。
ABOUT ME PAGEKit編集部 ホームページを最短15秒で作れる!PAGEKitは、誰でもかんたんにホームページを作成・管理できるサービスです。 私たちPAGEKit編集部は、ホームページをもっと便利に、もっと楽しく使っていただけるよう、日々TIPSや活用アイデアを発信しています。 |
ホームページかんたん作成のPAGEKit(ページキット) ホームページを作るのは、むずかしそう。 そう思っていた方も、PAGEKitなら「意外とカンタンだった」と感じていただけるはずです。 専門知識がなくても、必要なページがすぐに揃うテンプレートと、やさしい操作画面。 まずは一度、実際の使いやすさを体験してみませんか? |
