美容室のホームページ、自分で作れる?業者に頼むべき?

「お店のインスタは毎日更新してるけど、そろそろちゃんとしたホームページも欲しいな…」
「でも、"美容室 ホームページ"で検索すると、制作会社やツールの広告がずらっと出てきて、もう何が何だか…」
こんな風に感じたこと、ありませんか? いざホームページを作ろうと思っても、自分で作るべきか、プロの業者さんにお願いするべきか、最初の分岐点で迷ってしまいますよね。正直なところ、どちらの選択肢にも良い面と、ちょっと大変な面があるんです。
この記事では、特定のサービスをゴリ押しするのではなく、「自分で作る場合」と「業者に頼む場合」のリアルな情報をお伝えします。それぞれのメリット・デメリット、費用のこと、どんな人がどっちに向いているのか。あなたのサロンにぴったりの方法を見つけるお手伝いができれば嬉しいです。
そもそも、インスタだけじゃダメなんですか?

すごく良い質問だと思います。最近はインスタグラム経由で予約が入ることも多いですし、「わざわざホームページまで必要?」と感じるのも自然なことです。でも、ホームページにはインスタグラムだけではカバーしきれない、大切な役割があるんですよ。
「信頼の証」としてのホームページ
初めてあなたのサロンを知ったお客様が、お店の名前で検索したとき。そこにしっかりとしたホームページがあると、「ちゃんとしたお店なんだな」という安心感につながります。メニューや料金、スタッフ紹介、お店のコンセプトなどが整理されていれば、お客様は来店前に抱く不安を解消できます。これは、お店の「信頼性」をぐっと高めてくれるんです。
24時間働く、ウェブ上の受付窓口
ホームページは、あなたが寝ている間も、お客様対応をしてくれる優秀なスタッフのようなもの。予約システムを導入すれば、24時間365日、予約の受付が自動で完了します。電話予約だけだと、営業時間外や接客中は対応できませんが、ホームページがあれば機会損失を防げます。ブログ機能を使えば、お店のこだわりや最新情報を発信し続けることもできます。
ホームページを持つ意味、再確認リスト
- □ お店の公式情報として、お客様に安心感を与えられるか?
- □ ネット予約など、お客様の利便性を高められるか?
- □ お店のブランドイメージやコンセプトを伝えられるか?
- □ Googleマップなどで検索されたときの「受け皿」があるか?
選択肢は大きく2つ!「自分でコツコツ」vs「プロにおまかせ」
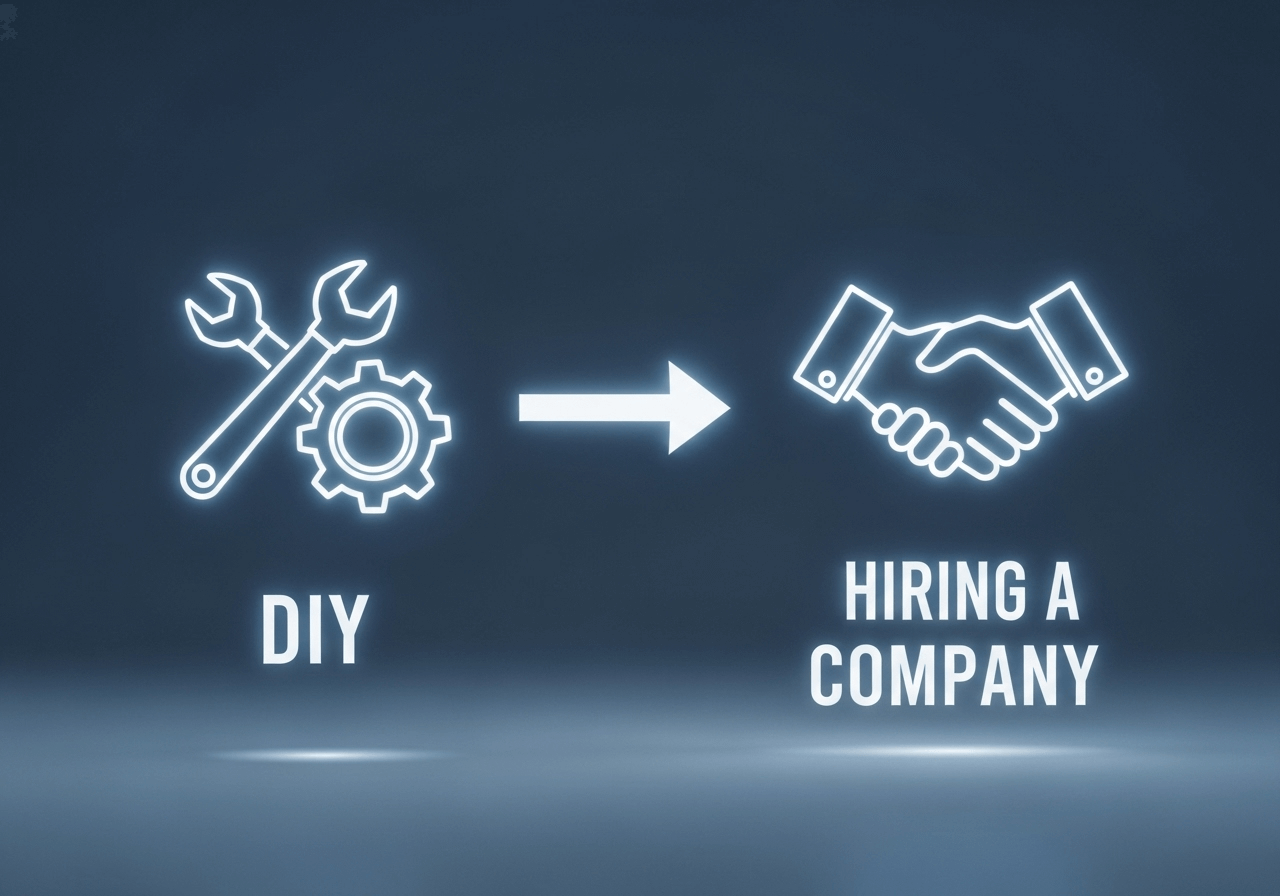
さて、本題です。美容室のホームページ作成には、大きく分けて「自分で作る」方法と「制作業者に依頼する」方法の2つがあります。まずはそれぞれのメリット・デメリットをざっくりと見て、全体像を掴んでみましょう。
それぞれのメリット・デメリット
どちらが良い・悪いということではなく、あなたのサロンの状況や、あなたが何を重視するかによって最適な選択は変わってきます。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
| 自分で作る | ・コストを大幅に抑えられる ・思いついた時にすぐ更新できる ・Webの知識が身につく | ・時間と手間がかかる ・デザインや集客の知識が必要 ・トラブル時に自己解決が必要 |
| 業者に頼む | ・プロ品質のデザインになる ・集客を考慮した設計をしてくれる ・本業に集中できる | ・費用が高額になりがち ・簡単な修正でも費用や時間がかかる場合がある ・業者選びが難しい |
「自分で作る」を深掘り!費用と手間を天秤にかける

「まずはコストを抑えたい」「自分のペースで作りたい」という方は、自分で作る方法が気になりますよね。最近は専門知識がなくてもホームページを作れるツールがたくさん登場しています。
どんな方法がある?主な2つのルート
自分で作る場合、大きく分けて2つの方法があります。
- ホームページ作成サービス: 専門知識がなくても、用意されたテンプレートやパーツを組み合わせて直感的に作れるサービスです。初心者の方にはこちらがおすすめです。
- CMS(WordPressなど): ブログシステムをベースにしたもので、デザインや機能の自由度が非常に高いのが特徴。ただし、サーバー契約や設定など、ある程度の専門知識が必要になります。
主要なホームページ作成サービスを比較
ここでは、比較的よく使われるホームページ作成サービスをいくつか公平にご紹介します。どれも無料プランや無料お試し期間があるので、実際に触ってみて感覚を確かめるのが一番です。
| サービス名 | 価格帯(月額・税抜) | 特徴 |
| Wix | 無料〜(広告非表示プランは1,200円〜) | デザインの自由度が高い。豊富なテンプレートと機能が魅力だが、多機能ゆえに操作が少し複雑に感じることも。 |
| Jimdo | 無料〜(広告非表示プランは990円〜) | AIが質問に答えるだけで簡単なホームページを作ってくれる機能も。手軽に始めたい人向け。 |
| ペライチ | 無料〜(独自ドメインプランは1,465円〜) | 1枚の長いページ(ランディングページ)を作るのに特化。操作が非常に簡単で、イベント告知などにも使いやすい。 |
| Goope | 1,100円〜(初期費用3,300円) | 飲食店や美容室など、店舗運営に必要な機能(予約、メニュー表など)が揃っている。 |
| Ameba Ownd | 無料〜(広告非表示・独自ドメインは要有料プラン) | Amebaブログとの連携がスムーズ。デザイン性の高いテンプレートが豊富。無料で始めやすい。 |
ドメインやサーバーのこと
無料プランでは、URLが「○○.wixsite.com/あなたのサイト」のようになったり、広告が表示されたりします。お店の公式ホームページとして信頼性を高めるなら、月額1,000円~2,000円程度の有料プランに加入し、「独自ドメイン(例: anata-no-salon.com)」を取得することをおすすめします。
「プロに頼む」を深掘り!費用と効果を見極める

「やっぱりデザインにはこだわりたい」「パソコン作業は苦手だから、丸っとお任せしたい」という場合は、制作業者に依頼するのが確実です。時間や手間を節約して、その分サロンワークに集中できるのは大きなメリットですよね。
気になる費用感はどれくらい?
一番気になるのが費用のこと。これは制作会社や依頼する内容によって本当にピンキリです。あくまで目安ですが、価格帯別にできることのイメージを持つと分かりやすいかもしれません。
- 10万円〜30万円: テンプレートをベースにしたシンプルなホームページ制作。小規模な制作会社やフリーランスに多い価格帯。
- 30万円〜80万円: オリジナルデザインでの制作。写真撮影や簡単な文章作成、基本的なSEO対策などが含まれることも。
- 100万円以上: ブランディングから考えた完全オーダーメイド。集客戦略の立案、高度なシステム開発、動画制作などを含む大規模なプロジェクト。
失敗しない業者の選び方
「高いお金を払ったのに、イメージと違うものができた…」なんてことにならないよう、業者選びは慎重に行いましょう。
制作業者選びのチェックリスト
- □ 美容室やサロンのホームページ制作実績が豊富か?
- □ 担当者とのコミュニケーションはスムーズか?こちらの意図を汲み取ってくれるか?
- □ 料金体系は明確か?(初期費用、月額費用、修正費など)
- □ 完成後のサポート体制(更新方法のレクチャー、トラブル対応など)はどうなっているか?
- □ SEO対策(検索で上位に表示されるための対策)に関する知識や実績はあるか?
契約前に確認したいこと
意外と見落としがちなのが、完成後の運用のこと。契約前に「ホームページが完成したら、更新は誰が、どうやって、いくらでやるのか」を必ず確認しましょう。自分でブログを更新できる仕組みになっているか、簡単な修正は月額費用に含まれるのか、といった点は非常に重要です。
あなたの状況別・実践的なアプローチ
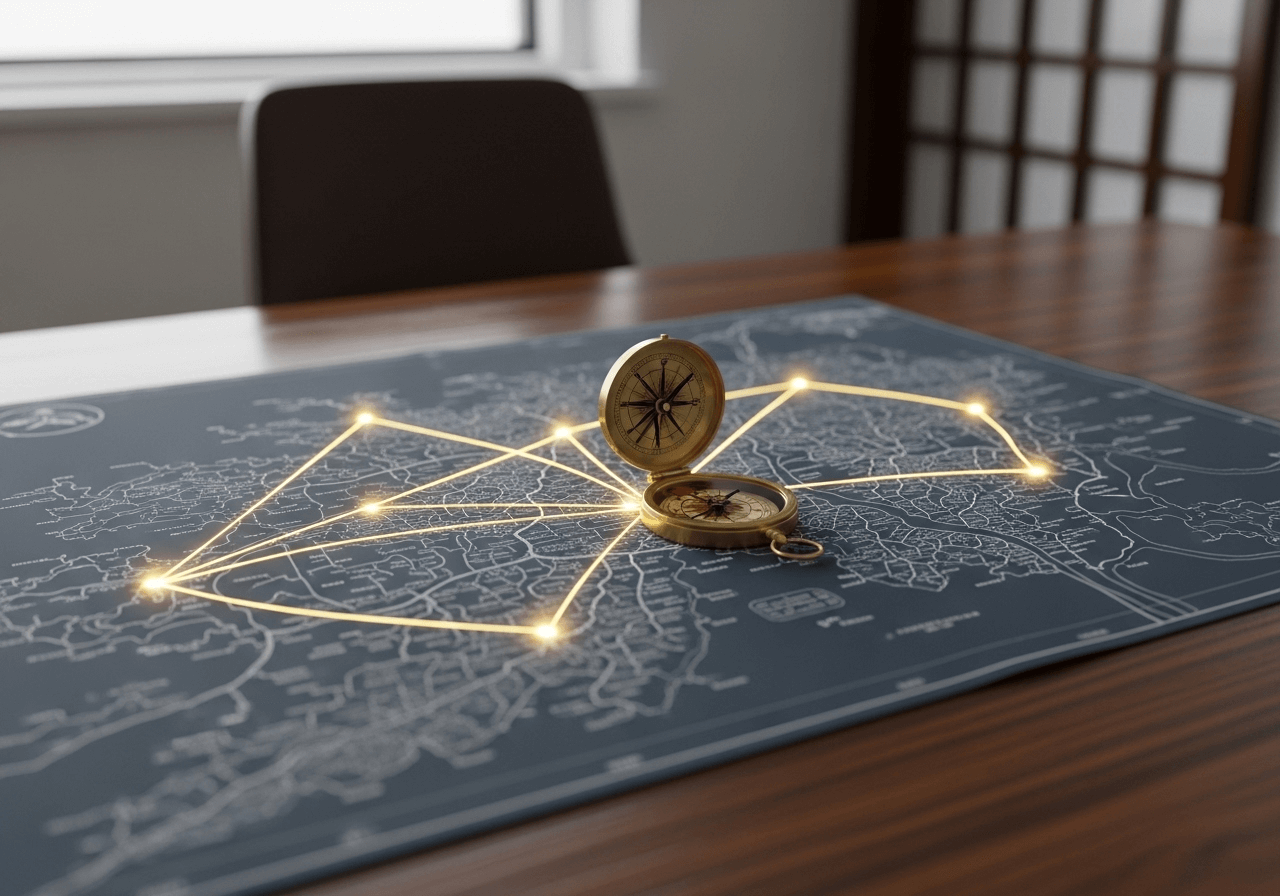
ここまで色々な情報をお伝えしてきましたが、「じゃあ、結局うちはどうすればいいの?」と思いますよね。そこで、あなたの状況に合わせた具体的なアプローチをいくつか提案します。
とにかく早く、安く始めたい方へ
開業したばかりで初期費用を抑えたい、まずはホームページという「名刺」が欲しいという状況なら、ホームページ作成サービスの無料プランや低価格プランで自作するのがおすすめです。完璧を目指さず、まずは「お店の基本情報(メニュー、アクセス、連絡先)が分かる」状態を作ることを目標にしてみましょう。運営していく中で、必要なものが見えてきたらリニューアルを検討すればOKです。
デザインや機能にこだわりたいけど、予算は抑えたい方へ
「パソコン操作はそこそこ得意。テンプレートのデザインじゃ物足りないけど、業者に頼むほどの予算はない…」という方。少しチャレンジングですが、WordPressでの自作を検討してみるのも一つの手です。学習コストはかかりますが、うまくいけば低コストで自由度の高いサイトが手に入ります。もしくは、テンプレートが豊富でデザイン性の高いホームページ作成サービス(Wixなど)の有料プランを使いこなすのも良いでしょう。
本業に集中し、集客までプロに任せたい方へ
開業準備で忙しい、Webのことは全く分からない、ホームページをしっかりとした集客ツールにしたい、と考えているなら、美容室の制作実績が豊富な専門業者に依頼するのがベストな選択かもしれません。初期費用はかかりますが、時間と労力を節約し、プロのノウハウを活用できるメリットは大きいです。複数の業者から話を聞いて、相見積もりを取ることを忘れずに。
まとめ
美容室のホームページを「自分で作るか」「業者に頼むか」。これは、どちらが正解という問題ではありません。あなたのサロンの今の状況、予算、かけられる時間、そしてホームページに何を求めるかによって、最適な答えは変わってきます。
- ・自分で作る:低コストで自由度が高いが、時間と学習が必要。PCが得意で、自分で試行錯誤するのが好きな人向け。
- ・業者に頼む:高品質で手間いらずだが、費用がかかる。本業に集中したい、Webが苦手な人、集客を重視する人向け。
- どちらを選ぶにしても、ホームページは「作って終わり」ではありません。情報を更新し、育てていくことが大切です。
- まずはホームページ作成サービスの無料プランを触ってみて、自分にできそうか感触を確かめてみるのも良い方法です。
この記事が、あなたのサロンにとってベストな一歩を踏み出すためのヒントになれば、とても嬉しいです。焦らず、じっくりと自分に合った方法を見つけてくださいね。
もし少しでも興味があれば、ホームページを作成してみませんか?
ここまで美容室のホームページ作成について詳しく解説してきました。記事を読んで「実際に取り組んでみたい」と思われた方に、少しだけ私達のサービスをご紹介させてください。
気軽にホームページが作成できる「PAGEKit(ページキット)」
「まずはホームページを立ち上げてみたい」「できるだけシンプルで分かりやすい料金体系がいい」と考えているなら、私たちが提供しているPAGEKitもご検討いただけると嬉しいです。
PAGEKitは、初心者の方でも安心してホームページが作れるよう機能をシンプルに、また、操作方法のお問い合わせにもすぐに答えられるようサポートをとても重視しています。
一人で悩みながら作るよりも、気軽に相談しながら作ってみませんか?
もちろん、この記事で紹介した他のサービスも、それぞれに優れた特徴があります。ぜひあなたの目的や予算に最も適した選択肢を見つけてくださいね。
ABOUT ME PAGEKit編集部 ホームページを最短15秒で作れる!PAGEKitは、誰でもかんたんにホームページを作成・管理できるサービスです。 私たちPAGEKit編集部は、ホームページをもっと便利に、もっと楽しく使っていただけるよう、日々TIPSや活用アイデアを発信しています。 |
ホームページかんたん作成のPAGEKit(ページキット) ホームページを作るのは、むずかしそう。 そう思っていた方も、PAGEKitなら「意外とカンタンだった」と感じていただけるはずです。 専門知識がなくても、必要なページがすぐに揃うテンプレートと、やさしい操作画面。 まずは一度、実際の使いやすさを体験してみませんか? |
